top of page

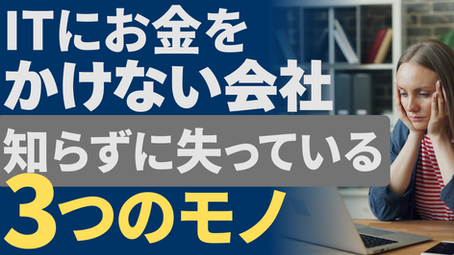
ITにお金をかけない会社が、知らないうちに失っている3つのモノ
「ITには、できるだけお金をかけたくない」 中小企業の経営者として、とても自然な感覚だと思います。 実際、 ・大きなトラブルは起きていない ・何とか回っている ・今すぐ困っているわけではない そう感じている会社も多いはずです。 ただ一方で、 ITにお金をかけないことで、気づかないうちに“失っているモノ”がある というケースも、現場ではよく見かけます。 今回は、その代表的なものを3つ紹介します。 ① 静かに削られていく「時間」 ITにお金をかけない会社で、最も失われやすいのが 人の時間 です。 ・PCの動作が遅い ・ちょっとした不具合が頻発する ・トラブルが起きるたびに調べる ・詳しい人を探して声をかける 1回1回は数分、数十分でも、それが毎日・何人分も積み重なると、かなりの時間になります。 社員の時間だけではありません。 「これ、どうなってる?」と経営者が確認に入る時間も増えていきます。 ITにお金をかけていないつもりでも、 実際には“人の時間”という形で支払い続けている 状態です。 ② トラブル時に失う「選択肢」 もう一つ、見えにくいのが 選択
1月6日読了時間: 3分


IT担当がいない会社が“やらなくていいIT対策”
「セキュリティ対策は大事だと分かっているけど、正直、どこまでやればいいのか分からない…」 IT担当がいない中小企業の経営者から、よく聞く悩みです。 ネットや営業の話を聞いていると、「これも必要」「あれも危険」と不安ばかりが増えてしまい、結果として 何も手を付けられない というケースも少なくありません。 でも実は、 IT担当がいない会社だからこそ「やらなくていいIT対策」もあります。 今回は、現場を見てきた立場から、「優先度が低い」「今は手を出さなくていい」IT対策を整理します。 ① いきなり高額なセキュリティ製品を入れること 「とりあえず有名なセキュリティ製品を入れておけば安心」 これは、よくある誤解です。 高額な製品を導入しても、 設定が初期状態のまま 誰も管理していない アラートが出ても気づかない この状態では、 ほとんど意味がありません。 IT担当がいない会社にとって重要なのは、 使い切れること 管理できること 日常業務に負担をかけないこと 製品選びよりも、 「今の運用に合っているか?」を考える方が先です。 ② 完璧なルール・細かすぎるI
2025年12月23日読了時間: 3分


USBメモリは便利だけど危険──中小企業が見直すべき“持ち運び文化”
「資料を家で作りたいから、USBに入れて持って帰りますね」 中小企業の現場では、いまだに当たり前のように行われている光景です。 しかし最近、USBメモリの紛失による情報流出事件が相次ぎ、深刻な問題になっています。 たとえば札幌市では、教頭が児童や保護者の個人情報を入れたUSBメモリを失くし、後日、匿名で返送されて発覚したケースがありました。 https://www.uhb.jp/news/single.html?id=48567 「うっかり落とした」 「つい持ち出してしまった」──これらは誰にでも起こりえるミスです。 USBメモリは軽くて便利。 だからこそ、 一度なくすと取り返しがつかない 。 今回は、中小企業が今すぐ見直すべき「USBメモリの持ち運び」について解説します。 ① USBメモリは“最も危険な記録媒体” USBメモリ自体は悪いものではありません。 しかし、ビジネスで使うにはリスクが大きすぎます。 ● 小さくて軽い → とにかく失くしやすい ポケット、バッグ、デスクの隙間……。どこにでも落ちます。 ● 暗号化されていない → 拾われたら
2025年12月5日読了時間: 4分


家庭用ルーターを会社で使うのは危険?──小規模オフィスで起きやすい“見落としリスク”
「とりあえずネットがつながればいい」 そんな理由で、家庭用ルーターをそのままオフィスで使っている企業は意外と多いものです。個人事業主や小規模オフィスでは特に、 自宅と同じルーター を持ち込んで利用しているケースがよくあります。 しかし、家庭用ルーターは“家庭で使う前提”で作られた製品。 業務利用では、見えないところで大きなリスクを抱えることになります。 この記事では、 なぜ家庭用ルーターは会社に向かないのか?どうすれば安全にWi-Fiを運用できるのか? を、専門知識がなくてもわかるように解説します。 ① 自宅と同じルーターをオフィスで使っていませんか? 個人事業主・小規模事業者の現場でよくあるのが、 自宅で余っていたルーターを使っている 家電量販店で買った安価なルーターをそのまま接続 設定は触らず“買ったそのまま”で運用 SSIDもパスワードも初期設定のまま というパターンです。 しかし、これらは企業にとって 非常にリスクが高い 状態です。 ② 家庭用ルーターが“会社利用に向かない”理由 家庭用ルーターは「家族が数台の端末をつなぐ」ことを想定し
2025年12月2日読了時間: 4分


PCが重い、遅い…放置していませんか?──中小企業がやるべき“定期メンテ”5選
最近、PCの動作が「なんだか遅い」「固まることが増えてきた」と感じる場面はありませんか?特に中小企業では、PCの不調を“仕方ないもの”として放置してしまうケースがとても多いです。 しかし、PCの動作不良は生産性を大きく下げ、場合によっては業務停止やトラブルにつながることもあります。 今回は、専門知識がなくても今日からできる“PCを快適に保つための定期メンテナンス”を分かりやすくまとめました。 ① PCが遅くなる原因は、実は“たった5つ” PCが重くなる理由は複雑に見えて、ほとんどが次の5つに収まります。 1. Windowsアップデートを放置している 仕事中に再起動が入るのが嫌で、「また後で」を繰り返し、気づけばアップデートが何十個も溜まっている…。これは非常に多いケースです。 2. ストレージの空き容量が少ない デスクトップにファイルが大量にある状態は要注意。 PCは“空き容量が減るほど”動作が遅くなります。 3. 不要なアプリや常駐ソフトが多い 使わないアプリを入れっぱなしにしていませんか? 知らないうちに常駐して動作を重くしていることがあり
2025年11月27日読了時間: 4分


メール添付はもう危険?──中小企業が避けるべき“古い仕事術”と安全なファイル共有の方法
業務のやり取りで、当たり前のように「メール添付」を使っている企業は多いと思います。 見積書、請求書、写真、資料…何でも添付して送るのが、昔からの習慣になっている会社も少なくありません。 しかし今、メール添付は 会社のデータを危険に晒す“古い仕事術” と言われ始めています。 誤送信、マルウェア、ファイルの混乱など、実務の中で発生するトラブルは数え切れません。 今回は、中小企業でも今日からできる、「メール添付をやめて安全にファイルを共有する方法」をお伝えします。 ① まだ“メール添付文化”を続けていませんか? 中小企業では、今も添付ファイルが日常的に使われています。 ちょっとした修正資料を送る 写真をまとめて送る 見積書や契約書をやり取りする 便利そうに見えますが、実は添付ファイルは セキュリティの事故が最も起きやすいポイント です。 クラウド共有が一般的になっている今、添付に頼るのは「リスクの高い働き方」になっています。 ② なぜメール添付は危険なのか? 添付ファイルが危険と言われるのには理由があります。 実際に多いトラブルを整理すると、次のよ
2025年11月25日読了時間: 4分


会社のPCを自宅に持ち帰るときの注意点──“よくある失敗”とトラブルを防ぐ基本ルール
外出先や自宅で仕事をする機会が増え、会社のノートPCを持ち帰るシーンは珍しくなくなりました。 「明日の資料を家で作りたい」 「急ぎのメールだけ自宅で確認したい」 「リモートワークだから会社PCを使う」 どの会社でもよくある場面です。 しかし、実はこの「PCの持ち帰り」が、 情報漏えいの入口になりやすいポイント でもあります。少しの油断が大きなトラブルにつながるため、最低限のルールを知っておくことが大切です。 ① 持ち帰りPCで起きやすい“よくある失敗” まずは、現場で本当に多いトラブル例を紹介します。 1. 自宅Wi-Fiにそのまま接続してしまう 家族が使っている端末にウイルスが入っていると、同じWi-Fiにつないだ会社PCにもリスクが及びます。 2. 私物USBメモリでデータを移動する 実務で最も多い事故原因です。ウイルス感染やデータ漏えいのリスクが非常に高く、会社からUSBの持ち込みを禁止しているケースも増えています。 3. 家族の前で業務画面を開いてしまう(のぞき見) 営業資料や顧客情報などが、家族に見られてしまうケースは意外と多いものです
2025年11月20日読了時間: 3分


無料Wi-Fiで仕事して大丈夫?──外出先で“やりがちな危険行為”と安全に使う方法
カフェや駅、ホテルのロビーなど、外出先で無料Wi-Fiに接続して仕事をする──いまではよくある光景です。 しかし、実は 無料Wi-Fiは ITトラブルが最も起きやすい場所 の一つ。 特に中小企業では、“会社のアカウントを個人PCで操作する”状況も多く、リスクが一気に高まります。 今回は、外で仕事する際に気をつけたいポイントを専門用語なしで、できるだけわかりやすくまとめました。 ① 無料Wi-Fiにはどんなリスクがある? 「無料Wi-Fi=危険」ではありませんが、“仕組みを理解しないまま使う”のが問題です。 1. 通信が盗み見られる可能性がある 同じWi-Fiに入った他の利用者から、 メール・ログイン情報・ファイルの中身 が覗かれてしまうことがあります。 特にHTTPSに対応していない古いサービスを使っているとそのまま見えてしまう場合もあります。 2. なりすましWi-Fi(偽物アクセスポイント) 攻撃者が本物そっくりのWi-Fiを作り、そこにつないでしまうと、どんな操作をしても すべて攻撃者に筒抜け になります。 名前が似ているWi-Fiは特に
2025年11月19日読了時間: 3分


社長だけパスワードが弱い問題──組織を危険にする「見えない盲点」とは?
社員には「セキュリティを徹底しよう」と伝えているのに、実は 社長自身のパスワードが一番弱い ──。 中小企業では、こうした状況が意外と多く見られます。 しかし、誰も社長に直接注意することができないため、問題が表面化しないまま放置されがちです。 ところが、最も守らなければならないのは、実は 社長アカウント です。 攻撃者にとって“最も価値の高い入り口”だからです。 ① なぜ、社長アカウントが危険なのか? 社長のアカウントは、一般社員とは比べものにならないほど 重要な権限 を持っています。 クラウドサービスの契約・請求情報 会社全体のデータアクセス権 社内の設定変更(管理者権限) 社外への信用に関わるメールやSNS つまり社長アカウントが乗っ取られると、 会社のほぼすべてを乗っ取られるのと同じ 状態になります。 攻撃者が狙うのは、セキュリティが強い社員のアカウントではありません。 “最も影響力があるアカウント”です。その筆頭が、社長アカウントです。 ② よくある「社長パスワード」の危険例 現場でよく見かけるケースをいくつか紹介します。 会社名+数字
2025年11月18日読了時間: 4分


まだパスワードだけ?──中小企業が多要素認証(MFA)を“最優先”で導入すべき理由
多くの会社で、ログインは「パスワードを入力するだけ」という状態が続いています。 しかし今の時代、 パスワードだけで会社を守るのはほぼ不可能 です。 ・パスワードの使い回し ・フィッシング詐欺 ・情報流出サイトからの漏洩 どれか1つでも当てはまると、外部からアカウントを乗っ取られる可能性があります。 しかも、もし1人のアカウントが突破されると── メール・クラウド・顧客情報・社内資料が、すべて攻撃者に見られる 状況になります。 そこで必要なのが 多要素認証(MFA) です。 “パスワード+もう1つ”の仕組みでログインを守る、今もっとも効果的な安全対策です。 ① パスワードが守りきれない時代 パスワードは、 見破られる 盗まれる 推測される フィッシングで抜き取られる あらゆるリスクにさらされています。 たとえば、攻撃者は漏えいしたメールアドレスやパスワードを自動で試し続け、たまたま一致したアカウントから侵入します。その際、狙われるのは必ずしも“社長や管理者”だけではありません。 一般社員1人のアカウントから、会社全体の情報が抜かれる。 これは今、
2025年11月14日読了時間: 3分


社員の“うっかり”が一番危険──小さな行動で守るセキュリティ習慣
「うっかりクリック」で止まる会社 ある日、B社(従業員20名の小さな建設業)の営業担当が、取引先を名乗るメールを開きました。「請求書データを確認してください」という件名。何の疑いもなく添付ファイルをクリックした瞬間、画面が止まり、ファイルが開けなくなりました。 実は、添付されていたのは ランサムウェア感染を狙う偽装メール 。その日のうちに社内サーバーのデータが暗号化され、取引先にも同様のメールが送られてしまいました。 幸い早期に気づき、大事には至りませんでしたが、復旧には3日を要しました。 社員は「自分のせいで会社が止まった」と肩を落としました。 しかし、B社の社長は叱ることなく言いました。 「誰にでも起こりうること。だから、次に備えよう」 そこから、B社の“セキュリティ文化づくり”が始まりました。 7割の攻撃は“人”から始まる サイバー攻撃というと、専門的な技術で突破されるようなイメージがありますが、 実際には 約7割が「人のミス」から始まっている と言われています。 メールの添付ファイルを不用意に開く USBやクラウドに無断でデータを保存する
2025年10月24日読了時間: 4分


被害を最小限にするために──中小企業が“最初の24時間”にやるべきこと
ある朝、ファイルが開けなくなった 月曜の朝。いつも通り出社したA社の社長は、社員からこう報告を受けました。 「共有フォルダのファイルが開けません。拡張子が見慣れない文字に変わっていて…」 画面には、英語で書かれた奇妙なメッセージ。 「あなたのデータは暗号化された。復元したければ、ビットコインを送れ。」 サイバー攻撃──ランサムウェア感染でした。 A社は社員10名の小さな製造業。IT専門部署はなく、システムは外部業者任せ。 「まさか、うちが…?」という言葉が社内に広がりました。 だがこの後、A社の経営を左右するのは “感染したこと”ではなく、“どう対応したか” でした。 最初の24時間で運命が変わる サイバー被害の現場では、 最初の24時間がすべてを決める と言われます。 慌てて操作したり、黙って様子を見ることが、被害を何倍にも広げてしまうのです。 被害を最小限にするために──中小企業が今知っておくべき、初動対応の基本を紹介します。 STEP 1:被害範囲を止める(拡大防止) 最初にすべきことは「止める」こと。調べたり直したりする前に、 感染を広げ
2025年10月23日読了時間: 4分


そのパソコン、誰のもの?──“端末管理”ができていない会社が抱える3つのリスク
「このパソコン、誰の?」から始まるトラブル ある中小企業で、社員が退職した後にパソコンが1台残りました。ところが、どの社員が使っていたのか分からず、パスワードも不明。ログインできないまま放置……。 似たような話、実は少なくありません。「うちは社員数も少ないから大丈夫」と思っていても、業務端末を明確に管理していない会社は意外と多いのです。 そして、トラブルや情報漏えいが起きたときに、 「誰のパソコンか分からない」=対応できない という状況に陥ります。 ① 紛失・盗難時に追跡できない ノートパソコンやUSBメモリなど、持ち運びできる端末は便利ですが、「紛失したら誰のものか分からない」というのが最大の問題です。 社外での打ち合わせやリモートワーク中に紛失した場合、管理台帳がなければ、機器の特定すらできません。 また、個人情報や取引先データが保存されていた場合、報告や対策が遅れることで、信用にも大きな影響を与えます。 管理できていない=責任を取れない。 端末管理は「トラブル後の行動」を決める準備でもあります。 ② 退職・異動時の端末が放置される 社員が退
2025年10月23日読了時間: 4分


「うちは関係ない」と思っていませんか? いま、サイバー攻撃の“狙い目”は中小企業です。
「うちは狙われない」という誤解 「うちは有名企業でもないし、機密情報なんて持っていないから大丈夫」そう考えている中小企業の経営者は少なくありません。 しかし、最近ニュースになっている大手メーカーへのサイバー攻撃をきっかけに、多くの中小企業が“他人事ではない”現実に直面しています。 実は、攻撃の多くは 特定の企業を狙ったものではありません。 攻撃者は、インターネット上に存在するあらゆるシステムを自動でスキャンし、 「守りが弱い会社」から順に侵入していく のです。つまり、狙われるというより「見つかってしまう」時代です。 中小企業庁やIPA(情報処理推進機構)の調査でも、 被害企業の約7割が中小企業 というデータがあります。しかも、被害の内容は「業務停止」「顧客情報流出」「取引停止」など、会社の信頼を直撃するものばかり。 なぜ中小企業が狙われやすいのか? サイバー犯罪者にとって、“中小企業は攻撃しやすい標的”です。その理由は単純で、「防御が弱い」から。 1. IT担当がいない、または兼務で後回しになっている 専任のセキュリティ担当者を置ける中小企業は多
2025年10月21日読了時間: 5分


IT担当がいない会社でもできる!セキュリティ運用の仕組みづくり
「セキュリティ対策が大事なのはわかっているけど、うちは専門のIT担当がいないから難しい…」 そんな声を、現場でよく耳にします。でも実は、セキュリティ運用は 専門知識がなくても“仕組み”で守ることができる んです。 この記事では、少人数の会社でも今日から始められる「セキュリティ運用の仕組みづくり」のステップを紹介します。 ステップ1:まず“守るべき情報”を整理する 最初にやるべきことは、 何を守るのかを明確にすること です。 会社の中には、次のようにさまざまな情報があります。 顧客データ(氏名・住所・連絡先など) 契約書や請求書などの重要書類 社内マニュアルや社外秘の資料 社員や取引先とのメール履歴 これらの情報がどこに保存されていて、誰がアクセスできるのかを把握することが第一歩です。 Google Workspaceを使っている会社なら、「Googleドライブ」の共有設定をチェックしてみましょう。 不要な共有リンクが外部に公開されていないか 退職者のアカウントにデータが残っていないか 機密情報が“全員に共有”になっていないか この確認だけでも、情
2025年10月7日読了時間: 3分
bottom of page
.png)